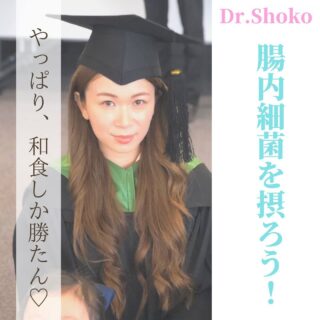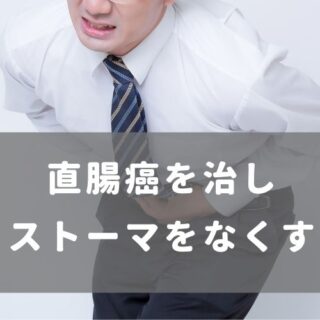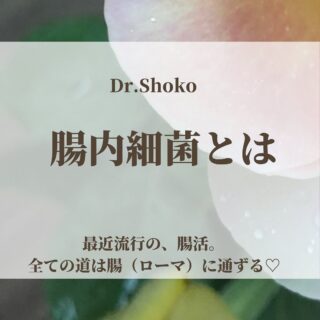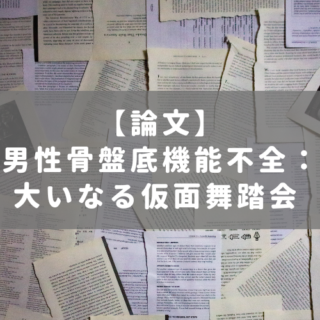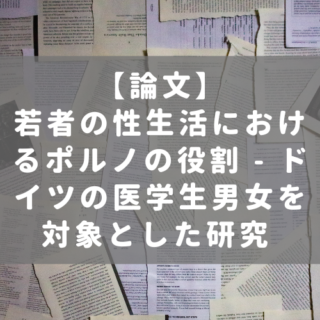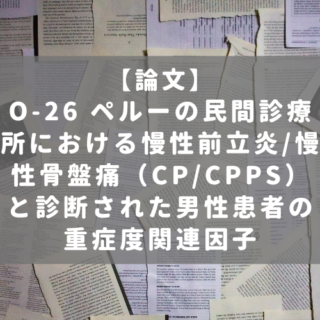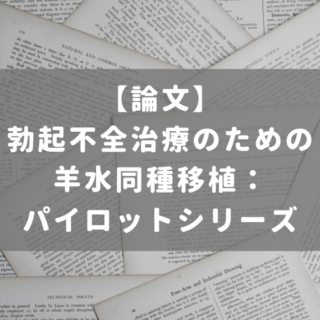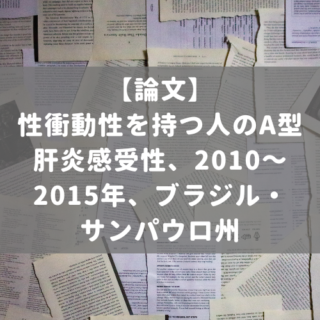Contents
痔瘻とは
肛門と直腸の境目である歯状線には肛門陰窩と呼ばれる、深さ1mmほどの溝が複数並んでいます。
ここに下痢が入り込み細菌が繁殖すると炎症を起こし、肛門周囲膿瘍を患うのです。
この肛門周囲膿瘍が進行し、溜まった膿が肛門の周囲から排出されると痔瘻になります。
肛門陰窩から伸びたトンネルは瘻管と呼ばれ、自然に閉鎖することはありません。
痔瘻の原因
痔瘻は男性が患いやすい痔です。
理由にはさまざまなものがありますが、その1つとして下痢の頻度が挙げられます。
痔瘻は下痢が原因で発生することが多く、ストレスや過度の飲酒でお腹を下しやすい男性は女性よりも患者数が多いです。
女性も例外ではなく、女性患者のうち5%ほどは痔瘻が発生します。
痔瘻の症状
痔瘻を患うと瘻管から漏れ出た膿が下着を汚し、悪臭を発します。
また痔瘻は悪化した化膿であるためズキズキと痛み、38度から39度の発熱を伴うことも少なくありません。
なお瘻管を封鎖しない限り、膿は常に出てきますので、治すには手術が必要です。
痔瘻の分類
痔瘻は瘻管が伸びる方向によって4種類に分別されます。
括約筋の間を通り、臀部の外へと伸びていくタイプは低位筋間痔瘻と呼ばれています。
このタイプが最も多く、全体の60%ほどです。
括約筋には内括約筋と外括約筋の2種類があり、外括約筋を超えた後に外へつながると坐骨直腸窩痔瘻になります。瘻管が肛門の後ろ側を複雑なルートで通るため症例は多くなく、全体の3割程度です。
括約筋の上にはさらに肛門拳筋という筋肉があり、その上にまで瘻管が至ると骨盤直腸窩痔瘻になります。坐骨直腸窩痔瘻よりも稀であり、治療が非常に難しいため、人工肛門になってしまうケースもあります。
なお骨盤直腸窩痔瘻は、直腸狭搾も起こしやすいです。
痔瘻のうち1割程度ですが、内括約筋と外括約筋の間を通り瘻管が体の上の方へ伸びてしまうこともあります。
この場合だと瘻管は外へとつながっていないので膿は排出されません。
痔瘻の治療について
痔瘻では、肛門陰窩で細菌が繁殖し炎症を起こす肛門周囲膿瘍を患います。
体の内側で起こっているものなので視認はできませんが、痛みや発熱など肛門周囲膿瘍の症状が出てきたら医者のもとへと向かいましょう。
肛門周囲膿瘍の治療法として、切開排膿とドレナージが主なものとして行われます。
これらの治療法により膿を排出させ、さらに抗生物質や鎮痛剤を投与したとしても、多くの場合は痔瘻として肛門の外にまでトンネルがつながります。
さまざまな手術法があります
痔瘻の手術法はさまざまあり、瘻管の通り方や原因によって手術法が変化します。
切開開放術
切開開放術は痔瘻の手術の中で最も再発が少ないです。
切開開放術では瘻管を切り開いて切除、その後場合によっては患部の左右を縫合し固定します。
痔瘻は瘻管の道筋によって区分され、皮膚の下を通っているⅠ型や括約筋の間を通って皮膚の外へと向かっているⅡL型に対して切開開放術は有効です。
一方で瘻管が上のほうへと向かっているⅡH型や複雑な道筋を辿っているⅢ型やⅣ型の場合、括約筋を傷付けてしまい結果として肛門が緩くなる、または形がいびつになる可能性があります。
そのため再発率が少ない手術法でありながらも使える機械は限られています。
なお瘻管が肛門広報部にある場合は、たとえ括約筋を切除しても機能への影響はありません。
括約筋温存術
Ⅲ型やⅣ型といった複雑な痔瘻の場合、括約筋温存術が行われます。
技術的難易度が高く、また再発の可能性も数%残ってしまうものの、括約筋を傷付けるおそれがないのがこの手術方法の特徴です。
括約筋温存術では痔瘻に沿って病巣をトンネルのようにくりぬくため、「くりぬき法」と呼ばれることもあります。
括約筋にメスを入れないだけでなく、切除の範囲も切開開放術より狭いため治癒が早いです。
シートン法
切開開放術と似た手術法としてシートン法が挙げられます。この手術法では瘻管の外側からゴム紐を通し、内側から出して縛ります。
体にとってゴム紐は異物であるため外へ押し出す反応が起こり、それによってゴム紐で縛られた組織、つまり瘻管の横側にある組織が小さくなっていきます。
この方法は肛門括約筋への負荷が少なく、切開開放術のように肛門の機能低下や変形が起こるリスクを負わなくて済むことが利点です。
しかしゴム紐の締め直しや入れ替えのために何度も通院しなくてはなりません。
さらに人体の反応に任せているため治癒までの時間が長く、平均して数ヶ月ほどかかります。
ゴム紐が通っている違和感も我慢しなくてはなりません。
Henley変法
切開開放術と括約筋温存術の中間的な手術法がHenley変法です。
この方法では瘻管の外側からある程度までで切開を留めて歯状線の外側にある括約筋を除去し、また状態に合わせてドレナージを施します。
Henley変法は肛門括約筋が硬く、原発巣(症状が始まった箇所)が大きい場合に効果的です。